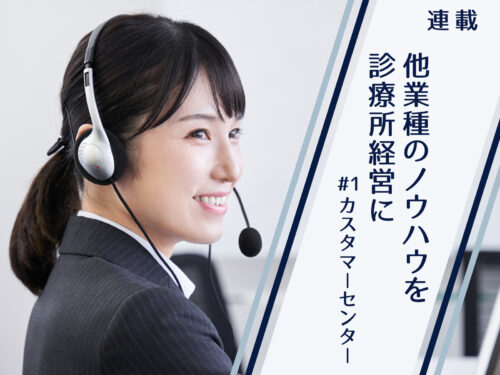自動車保険の担当者が語る「共感ベース」の関わり方がトラブルを減らし職場を良くする|他業種のノウハウを医療へ
接客業などに携わる人たちに聞く診療所でも役立つコミュニケーション術の特集。今回は、損害保険業界にお勤めの ゆゆさん(仮名)にお話しを伺いました。
ゆゆさんは、自動車事故の示談交渉や保険金査定をご担当のほか、部署マネジメントも担っていらっしゃいます。自動車事故時の交渉は、電話でのやりとりで相手の顔が見えず、さらに、興奮状態の人とのやりとりをすることもあるといいます。いかに冷静に対応できるかが求められる仕事です。
診療所でも、感情的な患者さんの対応や理不尽なことを言われる場面もあるかと思います。ぜひご参考にしてください。
そして、ゆゆさんは、グループを統括する立場でもいらっしゃいます。組織の中で、よい人間関係を構築するヒントもありました。
人によって異なる価値観 共感の気持ちを大切に
ゆゆさんは、自動車事故の被害者と交渉する部署に所属していて、お金と感情が絡む仕事のため、激昂し冷静にお話できない被害者といかに早く、納得感のある示談を行うかを考えなければならないといいます。
しかし、人の価値観は様々で、どのポイントで激昂するのか、どんな話法で懐に入れるかということを考えるのが大変だということです。
ゆゆさんの職場では、お客さんと接する中で以下のことを重要視されているといいます。
▼暴言を吐かれても、理不尽なことを言われても感情的にならない
▼相手の気持ちを察する
▼共感する
▼はっきりと断れる心の強さを持つ
ゆゆさんは、「いくら正論だとしても、相手の感情を逆撫でしては解決できない。いかに相手に味方だと思ってもらえるかが大切」だとして、人間味のある話し方を大切にされているそうです。
一度感情的になってしまったお客さんは、なかなか自分で振り上げた拳を下ろすことはできません。そんな時は、正論や理屈で責めるのではなく、会社の方針を変えることが難しかったとしても、一度引き下がり検討する姿勢、つまり寄り添う姿勢を見せることが大切だと話します。
対応できないことはしっかりと断るものの、断りの説明をしている時間よりも相手の気持ちに共感している時間を長くとるように意識しているということです。
診療所においても、待ち時間や診療内容など患者さんからの苦情などを受けることもあるかと思います。相手が感情的になっているときに誤った対応をしてしまうと、余計に過激になってしまうこともあります。
まずは相手にしっかりと寄り添って話を聞き、何に対しての苦情なのか、そしてどのような対応を求めているのか、的確に把握することが大切です。
相手が強い口調だったとしても、けんか腰にならない話し方、そして相手の気持ちに寄り添いながらも、断るべきことについては、毅然とした態度で対応することも大切なのかもしれません。
正しいことを言うときほど、言葉遣いや話し方を意識していきたいものです。
マネジメントする立場で良好な関係を築くために
ゆゆさんは現在、自身のグループを持ち、グループのマネジメントもしています。
部下と接する場面が多く、どんなことに気を付けているのか伺いました。
ゆゆさんは「とにかく褒める」ことを大切にしているそうです。ミスがあるとイライラしてしまう時もありますが、怒ることはしないということです。その代わりに、今回は失敗したけれど、その中でも頑張っていた点を評価し、次に気を付けて欲しいことを伝えています。
しかし、注意するなど厳しいことを言わなければならない場面も当然出てきます。そんな時、ゆゆさんは、「その後に他の仕事のことで褒める」ようにしているそうです。
仕事柄、社外から厳しい言葉を言われることが多く、働く仲間の心が折れないように社内は温かい雰囲気、自分の仕事に自信が持てるような雰囲気作りを心がけているそうです。
これはまさにどの職場でも活用できることではないでしょうか。指導する場面では特に言い方やタイミングなどに頭を悩ませている方もいらっしゃるかと思います。
ミスなどがあると、どうしても結果だけに目が行きがちですが、その過程で評価できる点や対応があったかもしれません。悪かったことだけ指摘するのではなく、よかった点も加えながら話すことで、相手の心を閉ざさずに話をすることができるのではないでしょうか。
ただ、診療所の信用に関わる問題など、しっかり指摘しなくてはいけない場面もあるかと思います。そんなときは、ゆゆさんのように、後日、その職員の良いところを認め、口にすることも大切なのかもしれません。
「いいこと見つけをする」そんな雰囲気が広がれば、互いを尊重し合う職場づくりに繋がるのではないでしょうか。
人に合わせた話し方を
ゆゆさんから、診療所でも活用できるコミュニケーション術のアドバイスをいただきました。
職員同士については、「失敗してもフォローしてもらえる、困っていたら助けてもらえる職場」このことが実感できれば、仕事上で苦痛なことがあったとしても職員が生き生きと働くことができると思います。
これは良好な組織をつくるために必要な「心理的安全性」に通じるものがあります。
心理的安全性とは巨大組織であるGoogleが効果的なチームとは何か?を探るプロジェクト・アリストテレスから生まれた言葉です。素敵なリーダーがいることよりも、報酬が高いことよりも、例え失敗しても程度が低いと思われる行動をしても、このチームなら大丈夫と思える心の安心安全があるところが一番チームとして効果が高かったという研究結果です。
そして患者さんに対しては、「老若男女、様々な患者さんが来院する中で、年齢層や特性に応じて話し方を変えることが大切なのでは」と、ゆゆさんは考えています。
例えば、高齢者は、女性の高い声が聞き取りづらいという傾向もあることから、落ち着いた声でゆっくりと話すこと。外国人に対しては、敬語の理解が難しい場合もあるので、簡単な日本語を使うことが大切なのではと。相手に合わせた話し方が大切ですね。
あとがき~言い方や話し方を大切にする~
今回は損害保険業界にお勤めの ゆゆさんに、お客さんや同僚とのコミュニケーションにおいて大切されていることを伺いました。
言い方や話し方はとても大切だということを感じました。同じ内容のことでも、言い方が違えば、相手への伝わり方も変わってきます。職場では良いことも厳しいことも言い合える関係性が必要な中で、相手を大切にできる言葉遣いを考えていきたいと感じました。
ぜひ診療所でも、患者さんに対して、そして同僚や指導する後輩に対しての言葉遣い、伝え方について考えてみてはいかがでしょうか。
ぜひ参考にしてください。
関連記事
おすすめ記事
まだデータがありません。